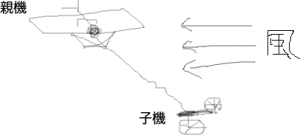結果を写しておこう。 本題に入るまえに、今回の地方選は結果を確認するのに非常に苦労した。この記事を見て読売新聞のサイトを知るまでは誰が当選したかも不明という…マスコミたまには仕事しろ。 知事選。
| 名前 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|
| 黒岩さん | 2195764 | 当 |
| 岡本さん | 665751 |
まあ当然の結果。争点もなく、この状況で現職を覆すのは難しいし、誰も立ち上がらなかった。正直この知事選は実にどうでもいい投票だった。 県議選。
| 名前 | 得票数 | 政党 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 川本さん | 28101 | 自民 | 当 |
| 滝田さん | 19813 | 民主 | 当 |
| 君嶋さん | 15002 | 共産 | 当 |
| 徳安さん | 11183 | 無所属 | |
| 日浦さん | 7871 | 維新 |
日浦さんは現職だったんですが、維新の不人気を受けた形。しかも本人の地盤もないので厳しかったろう。共産党は意外と支持を集めてるんですね。私は徳安さん当選すると思ったんだけどな。警察OBを再雇用して云々…とか、公約も練られていたように思いましたし、今年の朝の小杉では一番よく見た顔で、話にも内容があった。 市議選。
| 名前 | 得票数 | 政党 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 原さん | 10294 | 自民 | 当 |
| 松原さん | 9023 | 自民 | 当 |
| 市古さん | 8516 | 共産 | 当 |
| 末永さん | 6608 | 自民 | 当 |
| 重冨さん | 6311 | 無所属 | 当 |
| 押本さん | 6216 | 民主 | 当 |
| 川島さん | 6213 | 公明 | 当 |
| 大庭さん | 5948 | 共産 | 当 |
| 吉岡さん | 5524 | 公明 | 当 |
| 松井さん | 4584 | 民主 | 当 |
| 松川さん | 3880 | 維新 | |
| 潮田さん | 3573 | 民主 | |
| 小野寺さん | 3167 | 維新 | |
| 川村さん | 1233 | 無所属 | |
| 小林さん | 856 | 元気 | |
| 荒居さん | 799 | 無所属 |
いやー重冨さん(聖都・宮内から飛び立った鳥人間26歳)当選しました。この結果はなにげに衝撃的ですね。私も宮内人ぶって重冨さんに投票したクチですけど(笑)、こりゃ羽ばたいたな。なかなか凄いことですよ。がんばれよー。こっからだぞー。まあこの人、選挙運動してたのかどうかも謎だが。 あと川崎では維新は人気がない。川崎市全体でも惨敗状態で2人しか当選していません。中原区も2人立候補して両方落選、合わせて7000票。県議選の日浦さんの得票と同じくらいということから、維新の支持率は有権者20万人のうち7000-8000人、3.5-4%程度であることが分かります。みんなの党が消え、次世代とかいう片割れの党も潰れた末のこの体たらく。似た志向を持つ党がなく、うまくやれば近い思想を持つ有権者を総取りに出来た可能性もあったのにな…。石原さんに関わったせいで関東戦略には完全に失敗しましたからね。あの悪影響は大きかったと思います。 一方で自民党は3人立候補でベスト4の3枠を独占して全員当選、得票数は合計2万6千票。ぶっちぎりです。もう1-2人くらい立候補しても良かったと思います。 あとは共産党か。2人立候補で3位と8位に入って両方当選1万4千票。維新の倍、自民の半分以上。県議選の君嶋さんの得票数とだいたい同じですから、政党支持率がそのまま現れたものと思っていいと思いますが、有権者20万人の1.4-1.5万だから、約7%か。この数字は今回の選挙最大の驚き。立派な結果ですね。得票数は公明党の1.2万よりも多い。ひょっとしたらこれ行けるんじゃないの? と思わせる値。私としては信じられない気持ち。 民主党も厳しかったですね。富士通労組の団結力(…)をもってしても松井さんは滑り込みが精一杯。まあ議員数は3人立候補の2人当選なのでまあ惨敗とは言えない。合計得票数は1.4万票で公明党と共産党の間くらい。政党の埋没感に飲み込まれたか。