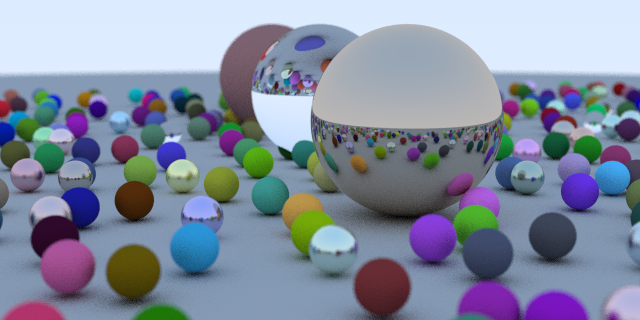画像生成が話題ということで、自分の手元のMBPでも動くということで、試してみている。普通のパラメータで動かすとさすがに1回1時間以上かかるけど、1枚きりの生成にすると2分弱で出てくるね。めちゃくちゃな時代になったな。こりゃーGPUも売れるだろうよ。
- watermarkが入れられているなー
- 少しいじって、出す.pngイメージのtEXtタグにpromptとseedの情報を放り込むようにしてみた
- 再現できるパラメータを全部くっつけた方がいいんだろうか
- 公序良俗に反するものはフィルタしているみたいだけど、マリオとかミッキーは平気で出してくるやべーやつ
とりあえず「専用スタジアムになった等々力」みたいな画像。ラインも周辺環境もぐちゃぐちゃですが…屋根ないのも困るなあ。
(WordPressに上げると.jpgに変換されて.pngのtEXtタグは消えちゃうんだな)