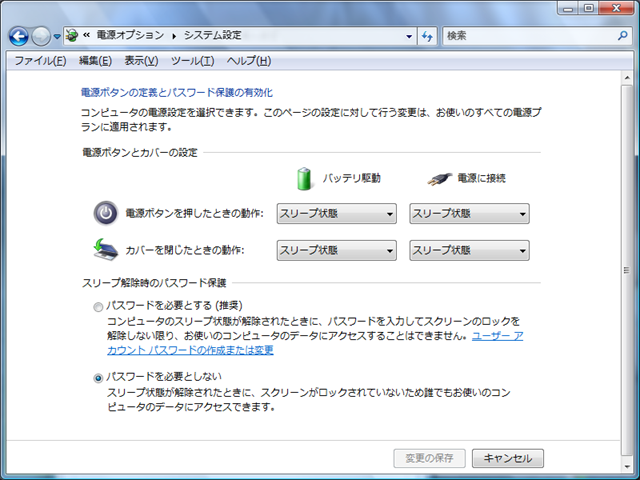状態:ダウンロード中 - 99%…という表示から変わらなくなって。だいたい放っておいたけど、よくよく考えると8時間くらい経過してる!
私が唯一管理しているWindowsマシンが1台だけ自宅にあるんです。Windows7からアップデートして使っているWindows10のマシンね。結局これだけはMacに移行できなかった。何年前のマシンだろう…転職する前だったはずだから、5年以上経つのか…調べたら2012年のことでした。それでも家族が普通に使えていたわけだが。
それで、1903の更新プログラムが見えたのでアップデートをかけてみたら、進まなくなったのよね。
ググるとストレージが弱いとそうなるとかいう話。**「ダウンロード中」という表示が嘘、**というのはいつものMicrosoftクオリティだから、まあ置いておこう。実際のところタスクマネージャで見るとCPUが50%に張り付いていて(2コアなので1コア使い切った感じかな?)、ネットワークもディスクもI/Oはまるで出ていない。完全にCPUネックではないですか。ディスク容量は半分くらいは残っているので容量が足りないってわけでもないはず。