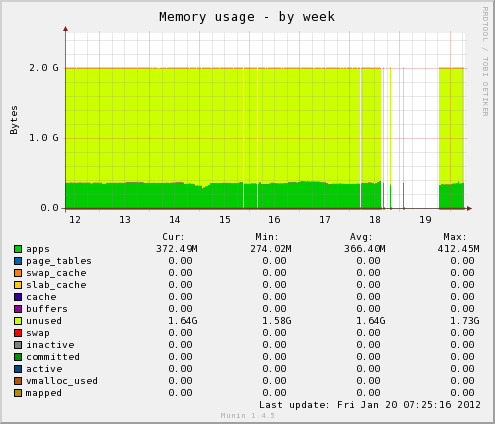使っているVPSがアップデートされました。
##
uname -srvmpio
Linux 2.6.32-042stab055.10 #1 SMP Thu May 10 15:38:32 MSD 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
これですね。1週間前にOpenVZからリリースされたカーネルです。アップデート以前はRHEL5ベースのカーネルでしたから、それをRHEL6ベースにしたということで、以前にアップデートに失敗していたものにリトライしたという感じ。うんこレベル寸前だった当時からだいぶ安定していたので乗り換え先の選定も進んでいない。
別にユーザランドはCentOS5なのでユーザとしての使い勝手に違いはないですが、/procに出てくるエントリもそれなりに増えてるのがまあ違いと言えなくもない。eventfdが使えるようになったのかな? CPU(Xeon L5520)とかは変わってないです。
それで、このVPS業者にはまだ選べるOSの選択肢の問題が残っている。「CentOS」とか「debian」で64ビットか32ビットは選べるんだけど、何とバージョンが書かれていないのだ。いま選んだらCentOS6になるのかな? それとも、5になるのかな??